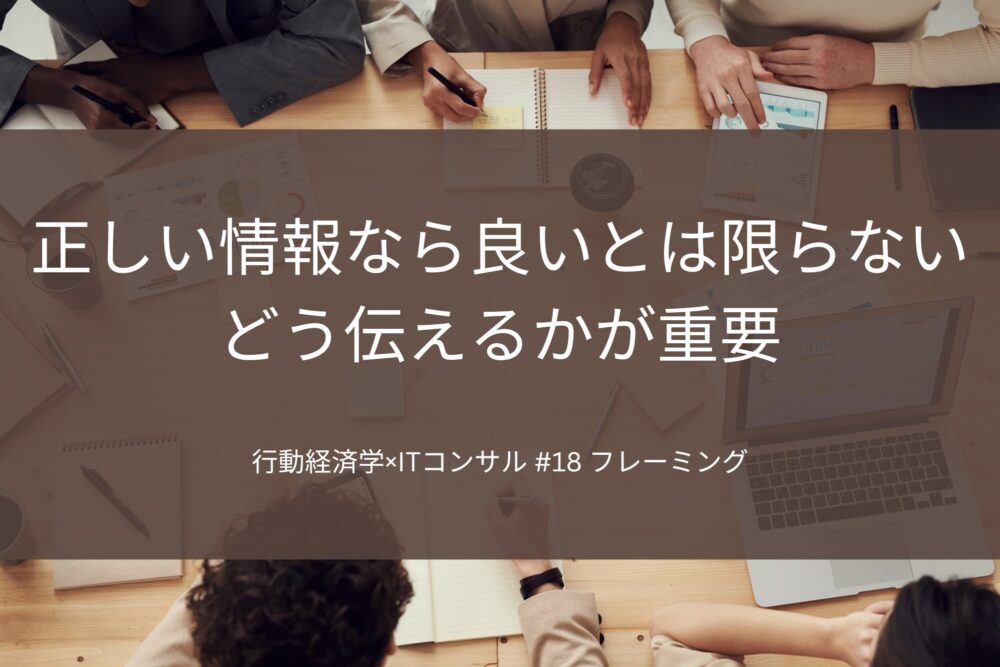ITコンサル業務に明日活かせるポイント
1) ポジティブとネガティブを使い分ける
2) 根拠となる数値を明確にする
3) マイナス情報はプラス情報とセットで提示する
行動経済学の理論(項目)の一つである、フレーミング – Framing – をもとに
ITコンサル実務で活用可能なポイントを紹介します
フレーミングとは
フレーミング効果とは、同じ情報でも、それを提示する方法によって人々の判断や意思決定が変化する現象のことを指します。言い換えると、情報の「枠組み」(フレーム)によって、人々の情報の受け止め方や、それに対する反応が異なるということです。
何事も言い方次第、ということですね
「90%の顧客が満足」と「10%の顧客が不満」では、
前者の方がポジティブな印象を持つでしょう
フレーミングの例の一つとして、
コップに水が半分もある
コップに水が半分しかない
というのもありますね
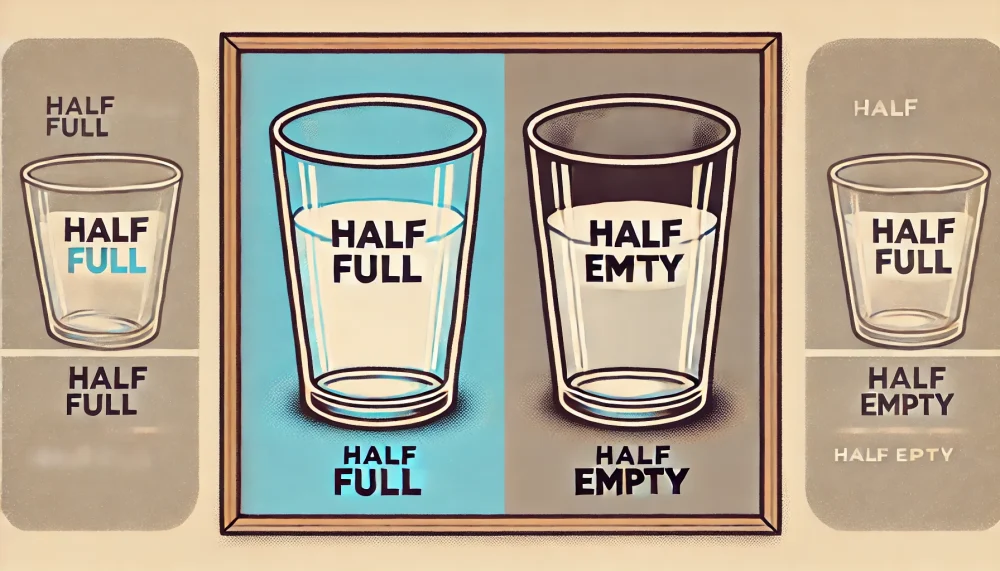
ITコンサルの業務への活用ポイント
活用ポイント1) ポジティブとネガティブを使い分ける
お客様の性質に応じて、ポジティブな見せ方をするのか、ネガティブな見せ方をするのかを考えましょう
提案活動では、提供するサービスについて基本的にはポジティブに伝えることになります
例えば、お客様から「採用事例はありますか?」と質問を受けた場合
実際には採用事例は国内で数件のみ、という場合であっても、
「これまで提案させていただいたお客様の採用率は100%です、数はまだ多くはありませんが」
などとお伝えすれば、ポジティブに伝わるでしょう
ポイントは、「これまで提案した中では」の部分でスコープを絞っている点です
スコープを絞ったことで、その中であれば100%の採用率と言えるようになりました
また、「他のお客様でも現在、採用が近い状況になっています」などと
他社がいい評価を下していることを匂わせるのも有効です
当然嘘はいけませんので、裏付けとなる情報はきちんと確認しておきましょう
また、お客様の健全な意思決定を阻害していないか、むやみな誘導をしていないかも注意しましょう
逆に採用されたくない場合は、意識的にネガティブに伝えることになります
例えば「まだ採用実績は数件しかありません、チャレンジ案件になりますね」
などと、「数件しか」や「チャレンジ」といった単語を入れることで
印象がかなり変わります
活用ポイント2) 根拠となる数値を明確にする
業務効率20%アップなど、何か定量的な数値を提示する場合
裏付けとなる根拠を確認し、提示する用意をしておきましょう
特にお客様が疑問を持っていなければ、無理に根拠を提示する必要はありません
ただし、根拠が存在しない場合はもはや嘘になる可能性もありますので
少なくとも事前に確認はしておきましょう
他人を責める前に、いったん立ち止まり、何か原因があるかもしれないと考えましょう
原因次第では、何か打つ手があるかもしれません
活用ポイント3) マイナス情報はプラス情報とセットで提示する
プラス情報だけを並べると、なんとなく疑ってしまいます
一方でマイナス情報が目立ちすぎるのは、それはそれでまずそうです
そこで、出し方としては
プラス情報を出した場合は逆のマイナスを
マイナス情報を出した場合は逆のプラスを出してバランスを取りましょう。
バランスをとった上で、与えたい印象の方を強調する形が良いです。
「現行システムの更改には半年、1億円かかります」
より、
「1億円かかりますが、今後5年間は保守コストが30%以上削減できるため、
十分回収できる見込みです」
などと出した方が意思決定しやすいですよね
お客様の上司も説得しやすいですし
1億円かかるという(お客様からみて)マイナス情報を出す必要があるため
マイナスを打ち消すようなプラス情報を添えて出しましょう
他にも
「新たにTrap監視を取り入れることで、これまでのPing監視のみに比べて、
詳細な情報を得られ、障害対応時間が短くなります(プラス情報)
監視サーバ側の対応や、運用担当の教育が必要になりますが。(マイナス情報)」
のように、プラス⇒マイナスの順序でもいいでしょう
まとめ
行動経済学の理論の一つ、フレーミングをもとに
人間はポジティブなことよりも、ネガティブなことを強く認識する性質を意識することで、どのような印象を相手に与えたいかをある程度コントロールできます
ポジティブな印象を与えたいのか、ネガティブな印象を与えたいのかを意識して、伝え方を変えましょう
というITコンサル現場での活用方法を紹介しました
ぜひ明日からの業務で意識していただければと思います
本ブログでは
行動経済学をお客様を良い方向、最適な方向に導くための効果的な方法の一つとして紹介しています
「自身の都合のいいように操る、誘導する方法」では断じてありません、ご留意ください
他にもITコンサルの現場で使える知識をブログで紹介していますのでご覧ください
ITコンサルだけではなく、SIerやSESの方々にも有益だと思います