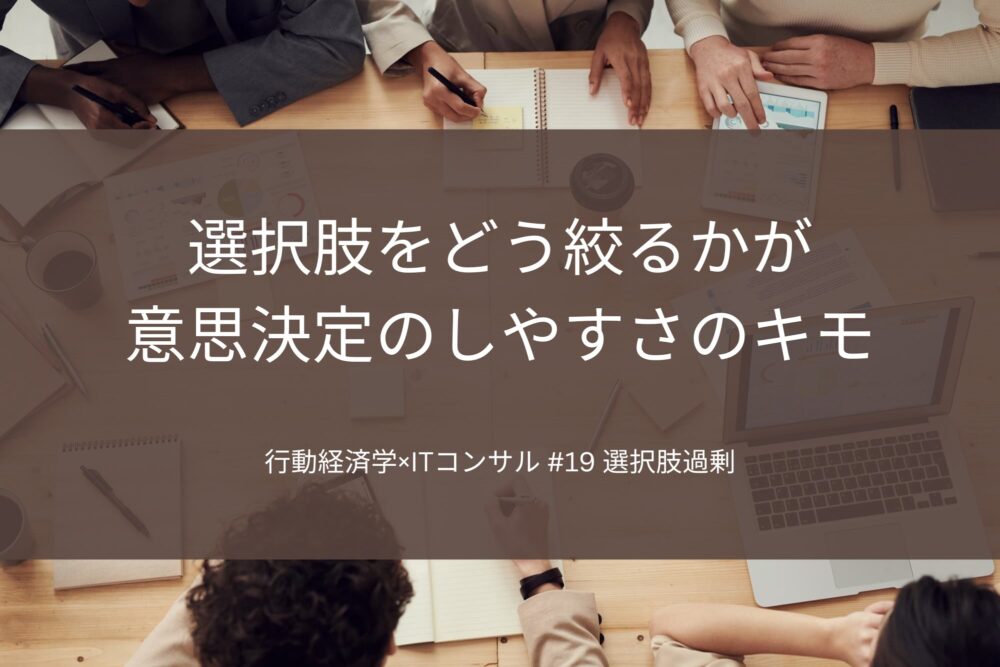ITコンサル業務に明日活かせるポイント
1) 情報はこちらが絞り、お客様に選ぶ負担をかけない
2) おすすめの選択肢を明確にする
行動経済学の理論(項目)の一つである、選択肢過多 – Choice Overload – をもとに
ITコンサル実務で活用可能なポイントを紹介します
選択肢過多とは
多すぎる選択肢は、消費者の購買行動にむしろ抑制をかける可能性がある
何かを選ぶ時、選択肢が多いと決めきれない心理です
「本日のおすすめ」が10種類あったら困りますよね
おすすめは1種類か、2種類ぐらいにしといてよと
実験の結果、種類が多すぎると選択に時間がかかるだけではなく
そもそも買われなくなる(諦める)可能性が高くなるそうです
選択肢を多く出すことは労力もかかりますし
お客様の多様なニーズに応えるため、提案者は頑張っています
しかし逆効果になってしまうということですね
選択肢は慎重に出す必要があります

ITコンサルの業務への活用ポイント
活用ポイント1) 情報はこちらが絞り、お客様に選ぶ負担をかけない
選択肢が多くなる場合、現在の案件における優先度を意識して
お客様が検討すべき案と、検討しなくていい案をある程度明確にすることが重要です
実質的な選択肢を減らす、ということです
例えば何かのシステムを設計する際、技術的な選択肢は6個(A~F案)あるとします
ここで、「お客様の環境を考慮すると現実的にはA案かB案かな~」
などと考えながらも、実施には6つの案全てを出す場面を多数見てきました。
案を出す側としては、
「色々考えてます」や
「抜け漏れはありません」など
色々と言いたいことがあるのはわかります
しかしお客様から見ると、選択肢がたくさんあって判断しづらいだけです
採用される可能性が薄い案については
「F案はXXXなどの特殊な要件の場合のみ視野に入ります」などとお伝えし
選択肢を絞っていく方向がいいでしょう
一方で、A案とB案だけに絞ってだすのも、それはそれで危険です
後で追加の要件などがでてきた際に「考えてなかったのでは?」と疑われる可能性があるためです
全部の案を出しておいて
「色々可能ではありますが、本件ではXXXの理由によりA案とB案だけ検討すればよいでしょう」
というように、お客様が考えやすくする形がよいと考えます
活用ポイント2) おすすめの選択肢を明確にする
選択肢をどうしても絞りきれず、3つや4つになってしまうこともあります
提示する側は、できる限り「おすすめ」の選択肢をお伝えしましょう
各案の優劣がそれほどない場合でも、です
よく見るのは「正しい情報をお伝えすればOK」と考えているのが
透けて見えるパターンです
例えば
「このバグに対するアクションとしては、AとBとCが提示されています」
のようなケースで
バグ情報自体は新しいものであり、
「自身が調べてもってきました!」と言いたくなるのかもしれません
しかしお客様はA, B, Cを提示されても、「結局どうすればいいの」になります
どの案にするかは、全面的にお客様側で考えてくださいというのは
ちょっと無理がある気がしませんか?
フラットに情報だけ提示するケースは本当によく見ます、気を付けましょう
案を提示するだけではなく、理由と共に、
「A案がおすすめです、なぜなら・・・」などとお伝えしましょう
本当に、どの案でもOK、という場合もありそうですが
お客様の環境だとちょっと実行しやすいとか、
リスクがちょっとだけ低いとか、何かしらの理由付けはできることが多いですので
なんとかおすすめを出していきましょう
まとめ
行動経済学の理論の一つ、選択肢過多をもとに
選択肢を絞って検討しやすくするため、お客様が検討すべき案と、検討しなくていい案をある程度明確にすることが重要。さらに情報を伝えるだけでなく、複数の案を提示する際はできる限り「おすすめ」の選択肢をお伝えすることで、お客様の負荷を減らせる。
というITコンサル現場での活用方法を紹介しました
ぜひ明日からの業務で意識していただければと思います
本ブログでは
行動経済学をお客様を良い方向、最適な方向に導くための効果的な方法の一つとして紹介しています
「自身の都合のいいように操る、誘導する方法」では断じてありません、ご留意ください
他にもITコンサルの現場で使える知識をブログで紹介していますのでご覧ください
ITコンサルだけではなく、SIerやSESの方々にも有益だと思います